asdm_public
ASD以外のハンディキャップ(二次障害、IQ、HSP、アファンタジアなど)
📒まとめ
- 二次障害。ASD 由来の不遇や負担によりうつ病、適応障害、不安障害など具体的な症状が生じる。このドキュメントでは対処には言及しません
- IQ。単に IQ が絶対的に低いか、相対的に低い場合もハンデとなりうる。性能不足の面で ASD と似ており、このドキュメントでも役立つ可能性がある
- HSP。繊細な特性による問題と見られる場合、ASD ではなく HSP の観点から捉えることで進展があるかもしれない。特にネット上には事例やノウハウが多数ある
- アファンタジア。ASD と同様、程度はスペクトラムだが、筆者の場合は「頭の中でイメージを扱えない制約」に等しく、配慮が必要なレベルと考える
===
ASDによるものとは限らない
ASD 部下がおこす問題は ASD が原因とは限りません。ASD とは関係のない、他の要因によって引き起こされている可能性があります。
あたりをつけていただくために、ASD 以外によく知られるハンデをいくつかご紹介します。
二次障害
ASD であることで「合わない」「上手く扱われない」「不遇である」状態が続くと、ストレスも溜まります。ストレスが溜まれば心身的な悪影響も出てきます。うつ病、適応障害、不安障害などはよく知られています。そもそも ASD に限った話ではないですが、ASD であることによってでも起きます。
🐰私の場合
一部を軽く紹介します。
- あったことの例:
- 明らかに向いてない仕事を任されており、その理由を説明しても受け入れてもらえず続行させられる → 終わるまで帰れず連日残業(上司が帰った後に帰っていた)
- 知識とスキルは周囲より強いにもかかわらず、生かしてもらえず、仕事を与えられないまま放置される or 雑用をやらされる
- 提案を見てもらえない、あるいは社交辞令で流される
- 組織での立ち回りに関するわかりやすいフィードバックが得られず、かつドキュメントなど情報もなく、いつまでたっても要領が得られない
- 無能やモンスターの扱いをされ、チーム内で軽視していい存在・無視していい存在・ネタにしていじっていい存在とみなされて扱われる、またそういう状況を黙認される
- 心身への影響の例:
- 円形脱毛症。頭部がまだらに剥げています。また眉毛と睫毛がありません。
- 狭心症(の疑い)。大きな病院をはしごして「疑いがある」「薬で様子見」まで行きましたが、それ以上は進展せず現在は回復しています
- フラッシュバック。タイムスリップ現象(*1 *2)として知られており、私の場合、当てはまるか微妙なところではありますが、突然過去の上司とのつらいやり取りがフラッシュバックしたり脳内で延々とバトルしたりして怒気と恐怖に満たされます
- 日常生活上の困難は(ひどくなければ)ありませんが、仕事の集中に差し支えたり気分が落ち込んだりはします
- 電話やメンションが来たとき、提案を一蹴されたとき、心理的安全性がない中で意見を出すときなどにもよく起きます
- リモートワーク中に起きると、ブツブツつぶやきながら激しい口論の練習をひとりで繰り広げることも多いです。また出社時でも人がいないときに行ったりします。ひどい場合は自席でつぶやくこともありました
- 個人的には「フラッシュバックというほどひどくはないが、タイムスリップ現象の範疇に入る程度ではある」「おそらく軽度」と理解しています
ですので、ハンデとして、たとえば以下のような機会損失があります。
- 不快な容姿(まだらに剥げた頭部、眉毛と睫毛のない顔面)によるメンタルへのダメージと機会損失
- ASD ゆえに自分勝手にそうしているのではなく、二次障害として起きたであろう円形脱毛症によって起きています
- ASD として容姿に無頓着であることが幸いして、平気になりましたが、そうでなければもっと精神的に深刻なダメージを負っていた可能性もあるでしょう
- また、気づいてないだけで、機会損失もしていそうです。まだらなハゲで、眉毛と睫毛がないのです。まして容姿をカバーするコミュニケーション能力もありません
- コミュニケーション機会からの逃避による機会損失
- 通常は問題ありませんが、配慮されないことが続くとタイムスリップ現象が増えてきて、自分からコミュニケーションを取りづらくなります
- 仕事が終わった後でも脳内で延々とタイムスリップしており、あまり休めず――との負のスパイラルにも陥ることがあります
- これらが重なると、期待する役割はまず満たされません。明確に問題が起きるか、キーマンが提案するなどして役割の変更、プロジェクトの離脱、異動などの措置が取られるまで続きます(あるいは単に放置したままプロジェクトが完遂します)。当然、このメンツからの印象は最悪で、次回以降の仕事には繋がりません
- 胸痛による機会損失
- 私はストレスは心臓に来るようです。そしてストレスの大半は、単に ASD としての配慮されないことによるものです。最近ではしっかり自衛しますが、場合によってはその場でうずくまるほど痛むことがあります
- 病院で検査してもらった頃の恐怖を知っており、もちろんまた来ない保証はないため、日頃からビクビクしています。胸痛は一種のバロメーターであり、痛くなってくると及び腰になりがちです
- タイムスリップ現象による機会損失
- 独り言が多く、怒気をはらんだ人物に見えるので印象は良くないでしょう
うつ病、適応障害、不安障害といったラインには至ったことはありません。覆水盆に返らずということわざもありますが、一度壊れたものは二度と元に戻らないと理解しており、私はそのラインには絶対に至らないと決意して自衛しているからです。しかし、私も鋼のメンタルを持つわけではないですし、自衛の過程で衝突して、悪い印象を持たれて、と機会損失は加速するばかりです。
このあたりの戦略は人次第で、二手にわかれます。私は自分を守るために衝突するタイプです。一方で、うつ病などにかかってしまう方は衝突を選ばず、自分が我慢して無理して合わせようとする印象があります。どちらがマシなのかはわかりませんが、私は壊れたら元も子もないと思いますし、壊れた自分を支えてくれるパートナーもいなければ、それを得るだけの力とモチベーションもないので、やはり自分を守る戦略を選びます(というより選ばざるをえない)。
IQ
ASDうんぬんというより、単にIQ(知能指数)が低いことによりハンデとなる場合があります。
知的障害
厚生労働省のページから引用します *3。
次の (a) 及び (b) のいずれにも該当するものを知的障害とする。
(a) 「知的機能の障害」について
標準化された知能検査(ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど)によって測定された結果、知能指数がおおむね70までのもの。
(b) 「日常生活能力」について
日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等)の到達水準が総合的に同年齢の日常生活能力水準(別記1)の a, b, c, d のいずれかに該当するもの。
IQ の数字で言えば 70 未満であり、さらに四段階に分かれています。
境界知能
IQ でいうと 71~85、つまり知的障害ほどではないが平均を下回る水準を境界知能と呼ぶことがあります。下記は NHK のページからの引用です *4。
小児精神科医・青山学院大学教授 古荘純一さん
「人によって差はありますが、境界知能の人の特性として、数的な処理が苦手、作業スピードが遅い、物事の理解が表面的、適切なコミュニケーションが苦手などあります。一見、その困難が周囲の人からはわかりにくいため、理解につながらず、困難な状況に陥っています。境界知能に起因する生活上の困難が原因で、ひきこもりや不登校などになっている人もいます」
ネット上ではグレーゾーンと呼ばれることもあり、啓蒙に勤める YouTuber もいらっしゃいます。
このドキュメントのスタンス
このドキュメントでは、IQ が高い場合は ASD の弱点をカバーできる可能性が高いとのスタンスを取っています。
また、IQに基づいたマネジメント――IQを構成する四指標のうち、得意なものを生かし苦手なものを遠ざける形の生かし方も提案しています。
IQ の低い ASD 部下のマネジメントについて
このドキュメントでは直接的には扱いません(筆者にナレッジがありません)。
生かせる可能性はある
しかし、生かせる可能性はあります。
このドキュメントでは全体的に「頭の性能」「認知能力」といったキーワードで、性能や能力に乏しい場合にどう扱えばいいかに言及することが多いです。特にASD の三大困難であるコミュニケーション困難、こだわりの強さ、コスパの悪さにとらわれないような働き方、仕事のやり方や考え方を重視しています。たとえば、
- ❌対面口頭で即座に反応を求める
- ⭕指定秒数の間、黙って考える時間を与える(たとえば10秒)
- ⭕なるべくテキストコミュニケーションを行う 整備をする(ITエンジニアは身近でしょうが、組織の生産性や働き方そのものを向上する足がかりになります)
- ❌専門用語、ジャーゴン(内部用語)、バズワード等の言葉の意味を曖昧にしたまま、コミュニケーションを行う
- ⭕言葉の定義をすべて明示的に行う
- ❌指示や期待を察してもらうこと前提で曖昧に行う。あるいは口頭で一度だけ行う
- ⭕きちんと言語化した上、必ずテキストで残して届ける(決まってない部分は決まってないと書けば良い)
- ⭕ASD部下がメモをして理解するまで待つ
- ⭕録音や録画を有効にしてから指示を出す。またはASD部下に録音や録画を許可し、自分で取ってもらう
といったことです。生かせることも多いと期待します。具体的な原則やテクニックも多数挙げておりますので、ぜひ漁ってみてください。
絶対的に IQ が低い場合は、おそらく無力
「IQ が低い」には二つの意味があります。
まずは境界知能など絶対的に低い場合です。この場合、いわば IQ の低さと ASD 由来の認知能力の欠如がダブルで来ている状態であり、このドキュメントでは手に負えない可能性があります。
特に、このドキュメントでは、ASD 部下自身にもある程度の能力水準を期待します。ひとりで日常生活をおくれる程度の地力という言い方をしています。この水準に満たない場合、おそらく本ドキュメントは役に立ちません。
相対的に IQ が低い場合は、おそらくありえるし有益である
もう一つが「相対的に」IQ が低い場合もあります。
仮に平均ラインの 100 を超えているから安心とは限りません。平均 IQ=120 の集団に IQ=100 が混ざっている場合、単純計算でこれは IQ=100(平均)の集団に IQ=80(境界知能)が混ざっているのと同じです。
「IQ が 20 違うと会話が成り立たない」との俗説がありますが、私はあながち間違ってないと思います。IQ が 20 違うということは、頭の性能の桁が違うということであり、下位側は上位側についていけないし、上位側は下位側の遅さをいちいち待っていられないから成立しにくくなると考えます。言葉で「寄り添えばいい」「IQ だけがすべてではない」というのはかんたんですが、いざ仕事で、自分より IQ が 20 低いメンバーや部下と恒常的に付き合うことになったら……? を考えてみてください。まして相手は ASD でもあるのです。
正攻法では難しいでしょう。難しいので、結局その ASD 部下を荒療治しようとして衝突するか、諦めて放置して天命に任せるか、ひどい場合はイジメのような構図が出来上がってしまいます。ASD 部下はもちろん、上司のあなたを含むチームや組織の全員に悪影響が出ます。あなた自身が病んでしまうリスクもありえます。稀に内部の不和では済まないトラブルに発展することすらあります。
しかし、前述したように、性能が悪いなりの扱い方を上手く適用することで、被害を最小限に抑えた共存が可能です。また強みを生かせれば、平均以上の成果や改善も出せるかもしれません。すべては上司でありマネージャーでもあるあなたのマネジメント次第なのです。
HSP
HSPとは Highly Sensitive Person の略であり、生まれつき感受性が強くて、敏感な気質を持つ者を指します。
HSPのルーツ
以下引用します *5。
HSPは心理学が発祥の言葉で,精神疾患の診断基準「DSM-5」にも記載されていません。つまり疾患名ではないのです。
HSPのルーツは,アメリカの臨床心理学者エレイン・アーロンが,1996年にThe Highly Sensitive Person: How to Thrive when the World Overwhelms Youという一般書を出版した時まで遡ります。翌年,パーソナリティ・社会心理学の分野で著名な研究雑誌Journal of Personality and Social Psychologyに,エレイン・アーロンとその夫で(「吊り橋効果」でも知られる)社会心理学者のアーサー・アーロンの連名で,HSPに関する研究論文が発表されました。これが学術的にはHSPの初出となります。
🐰私のカジュアルな理解
繊細さん(ちなみに商標のようです *6)の言葉にも代表されるように、HSP はカジュアルには「特に繊細な人」くらいの意味として用いられていると思います。
私は一理あると思っていて、たとえばオフィスワークの文脈でいくつか例を挙げると、
- 聴覚が敏感で、オフィスの喧騒でも疲弊するので耳栓やイヤーマフが欠かせない
- パーソナルスペースが人並以上に広く、一般的なレイアウトで隣に人がいるだけでも落ち着かなくて仕事どころではない
- 人の機嫌や雰囲気の察知に敏感で、険悪な態度やムードには到底耐えられない
こういった例は「社会人なんだから我慢しろ」では済まないものでしょう。済まないほど敏感な人達がたしかに存在する点には私も同感です。
ASD とは、学術的には連携していないように見えますが、性質としては被る部分があります。ASD も一部の感覚が敏感なことがあり、それに対処するための何らかのこだわりを持つことが多いはずです。
私の例も一つ挙げましょう。
- 5:00~21:00 の朝型生活を神経質に維持するとのこだわりを持っている
- これは「人混み」を避けるためであり、あまり自覚はありませんが、HSP 的な敏感気質が結構あると感じる
- 先日(2025/07下旬)、大阪旅行に行った:
- 人が多い万博には一切触れず、ホテルにこもってのんびりするか、ゲーセンで遊ぶか、地下街を散歩していた
- 当然 5~21 時も維持している
- 昼食は 9~10 時、夕食は 15~16 時
- そもそも旅行も早めの夏休みを使う形で、ド平日に行った
という感じで、人混みを避けることに徹底しており、旅行ですら耐えられるものではないようです。これを HSP と言っていいかは不明ですが、無視できないほど敏感であるとは言えると思います。
と、学術的に理解するには乱暴ですが、このようなカジュアルな広まり方をしたからこそ、ネット上には多くのナレッジが転がっていると感じます。ビジネス書と同様、実践的なジャンルと理解するのが良いと思います。
というわけで、もし ASD 部下の問題が「敏感な気質ゆえのもの」だと考えられる場合、HSP に関するナレッジから攻めると打開策が見つかるかしれません。参考までに、Deep Research の結果も置いておきます。これを書いているのは 2025/08/08 ですが、ちょうど OpenAI から GPT-5 が出た日であり、私も早速使ったのでした。生成 AI は便利ですね。
アファンタジア
頭の中でイメージを浮かべられない特性をアファンタジア(Aphantasia)と呼びます。よく使う説明は「りんごを思い浮かべてみてください」であり、アファンタジアは浮かべられません。
2025年現在、医学的に症状として認められたものではありませんが、研究や共有は進んでいます。国内でもひとりで情報を調べたり、当事者やコミュニティに接触したりもできる程度には知られてきたかなとの印象です。
ルーツと動向
Deep Research をご覧ください *8。以下いくつか引用します。
ルーツ。
2015年に英エクセター大学のアダム・ゼーマン教授(Adam Zeman)らが21名の生来イメージを持てない人々を報告する中でこの用語を初めて提唱……ゼーマンらはアファンタジアを「自発的な心的イメージが極度に低いか欠如している状態」と定義し、過去には「心の眼の喪失(mind’s eyeの消失)」など様々な呼称で報告されていた現象に正式な名称を与えた
原理はまだ解明されていないが、研究は進んでいる
大脳におけるメカニズム……ところがアファンタジアの人の場合、「思い描こう」と試みた際にも一次視覚野は一応活動するものの、その活動が意識に昇らず映像として知覚されないことが最新の脳画像研究で示されています
脳内ネットワークの観点では、記憶を司る海馬と視覚野の連携不全が関与するという知見……アファンタジア当事者は過去の出来事を思い出す(自伝的記憶想起)際に正常な人より海馬の活動が低下し、逆に視覚性後頭葉の活動が高くなる傾向……特に海馬と後頭葉視覚野の機能的結合(コネクティビティ)が極端に弱く、両者の活動が負の相関を示すことが報告
視覚イメージに頼らない認知
認知面での代償戦略や強みも観察されています。視覚イメージに頼れない分、アファンタジアの人は物事を記憶・思考する際に言語的・論理的な符号化を使う傾向があるとされます。例えば部屋のレイアウトを記憶する課題では、像を思い浮かべる代わりに「窓が左壁に1つ、テーブルは中央」と言語化して覚えるため、かえって曖昧な偽記憶を混入しにくいという実験結果も報告
情動体験を和らげることのメリデメ
さらに興味深い点として、情動反応やメンタルヘルスへの影響があります。心的イメージが浮かばないことは、一部の情動体験を和らげる利点にもなり得ます。例えば恐怖や不安を引き起こすような場面を想像できないため、トラウマ的記憶のフラッシュバックや将来への過度な不安イメージにとらわれにくいという報告
その反面、将来に向けたポジティブなビジョンを描いてモチベーションを高めるといったことも難しいため、創造的な発想法には違いがあるでしょう
現在では一つの研究領域のポジション
研究の広がり: アファンタジアは2015年に命名されて以来、短期間で世界的に研究が活発化しました。最初の論文発表から約10年足らずで関連研究は50報以上にのぼり……ゼーマン教授自身も2024年に過去10年の知見を総括するレビュー論文(Trends in Cognitive Sciences誌)を発表し、アファンタジア研究が一つの領域として確立しつつあることを示しました
人口の約1~3%
アファンタジアは当初「珍しい心的現象」と考えられていましたが、現在では人口の約1~3%程度が該当する比較的一般的なバリエーションであることが明らかになっています
白黒ではなくスペクトラム
ただし「像が全く浮かばない」度合いにも個人差があり、心的映像能力のスペクトラム(連続体)の一端に位置する概念……当事者の中には視覚だけでなく聴覚や嗅覚など複数の感覚イメージ全般が浮かばない人もいれば、視覚だけが特異的に欠如する人もいることが報告
公言している著名人
- エド・キャットムル(Ed Catmull)氏
- キャットムル氏はピクサー&ディズニーの元社長で3Dコンピュータグラフィックスの先駆者として知られますが、自身は頭の中に映像を全く思い描けないと告白し大きな注目を集めました
- ブレイク・ロス(Blake Ross)氏
- Mozilla Firefoxの共同開発者で、2016年に自身のFacebook投稿「頭の中で見えない世界 (Aphantasia: How It Feels to Be Blind in Your Mind)」でこの体験を書き綴りました
- クレイグ・ヴェンター(Craig Venter)氏
- ヒトゲノム解読を主導した米国の著名な科学者ですが、頭にビジュアルを思い描けないことが創造性の妨げにはなっていない好例としてしばしば言及されます
🐰あるアファンタジアが見る世界
筆者もアファンタジアを自負しています。
- 脳内でイメージを浮かべることができない
- 厳密に言えば、一瞬だけ浮かべられている気がしないでもないが、よくわからない
- 🐰「浮かべられているかどうかがわからない」が正直なところであり、わからないならできてないのでは?アファンタジアでは?と理解しています
- 地図を読みながら目的地に行けない
- 現実の景色と地図を対応付けることができない
- 頭の中でイメージを使えないのだから、やりようがない
- やるにしても「右にセブンイレブン●●店がある状態で、左の道を直進する。左にローソンが来る位置で停止し、ローソンの方を向き、そこから135度右に向いたときに正面(厳密に言えばもっとも角度的に近い道)に見える道を進み――」のように、解釈がブレないレベルで言語化してそのとおりに従う
- 🐰なので一つでも狂うと、もう迷います。迷ったら最期、ローラー作戦するしかなくなります。2025年現在はスマホを持っているのでその場で調べ直せるし、Googleマップは方向も表示してくれるので見比べもしやすくなりましたが、それ以前は認知資源節約の観点でスマホすら持っておらず本当に大変でした。もちろん、道も尋ねますが、聞いた内容を処理できないのであまり効果がありませんでした(とりあえずあっちに行けば良いくらいはわかるので無いよりはマシ)
- 言語的・概念的な記憶から 毎回その場で創作する
- たとえば「ふくろうを書いて」と言われると、ふくろうの特徴を思い出しながら、その場で創作する
- 以下に、あるとき私が実際に描いたふくろうを置いておきます。
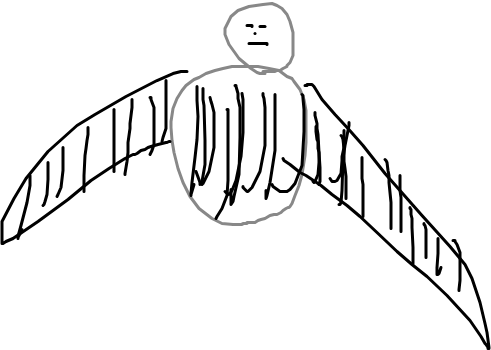
これはこのとき(2025/03、5:30頃)の創作にすぎません。描いた後の感想メモを見ると「足や爪があることを思い出せなかった」などと書かれていますし、このときの私は、ふくろうという概念に「羽を広げている」という情報をぶら下げていたのだと思われます。今同じことをすると、違うふくろうが生まれるでしょう。たぶん羽を閉じているふくろうを描くと思います。
例はこのくらいにしておきますが、一言で言えば、私は 頭の中でイメージを扱えない呪いがかかっている ようなものです。記憶面や情報処理面で極めて不利です。言語化や概念化でカバーはできますが、 イメージが使える人達の解像度には到底及びませんし、変換自体も疲れます。
仕事でもパワポやウェブサイト作成のようなビジュアルに寄った仕事はまずできない(私はできてるつもりだがメンバーや先方から OK が出ない)ですし、システム構成図のような作図も不可能です。かわりに、私はかんたんな図と、箇条書きなど構造的なテキストで表現しようとしますが、読んでもらえません。
一方で、言語化や概念化はずいぶんと鍛えられたと思っています。このドキュメントを書くくらいは造作もないことですし、まさにこのような力が求められるプログラミングやソフトウェア・エンジニアリングは私の十八番であり、本職です。最近では知的生産の名のもとに新しい概念をつくっています。
と、話が逸れたのでこのくらいにしておきますが、ともかく、アファンタジアの実例を一つ示せたと思います。
参考
- 1 自閉症の精神病理, 2016, 杉山 登志郎 pdf
- 2 GPT-5 Deep Research: https://chatgpt.com/share/68954b64-5d90-8007-913b-757f0c636a57
- 3 知的障害児(者)基礎調査:調査の結果|厚生労働省
- 4 境界知能とは 特徴は 検査でIQ81と判明した女性 仕事や学習で長年悩むも“支援がない” - NHK
- 5 心理学ワールド 98号 「正しさ」を考える 最近よく聞く“HSP”ってなんですか? - 日本心理学会
- 6 登録6611169、登録6449043。2025/08/08 時点
- 7 GPT-5 Deep Research「HSPの定義と対処方法」
- 8 GPT-% Deep Research「アファンタジアの研究状況」
- 9 注意欠如多動症(ADD,ADHD) - 19. 小児科 - MSDマニュアル プロフェッショナル版